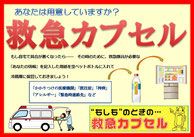過去のお知らせ
◆ 2016年度(平成28年度)
7~8月度 ふれあいトレーニングハウス開催日程表
注意: 7月からは、盛夏でもあり週2回の開催となります。また、火曜日の開催は
今までどうり石田先生のご担当です。
木曜日については鶴見区福祉センターの講師さんによる百歳体操となります。
~~各種イベント情報はこちらをご覧下さい。~~
◆ 2015年度(平成27年度)
ふれあいトレーニングハウスについて
★ふれあいトレーニングハウス★
皆さん、膝や腰、そして肩こりや頭痛で悩んでませんか❓
テレビや雑誌、ネットなどで健康体操や簡単な体操器具を使用して驚くほど
症状が改善した事例などが紹介されています。
それは、年齢とともに劣化する筋肉を、体操や健康器具で鍛える事により
いろんな症状の緩和や回復に繋がるからです。
緑・ふれあいの家では、2015年度「新規事業」として5月14日から
『ふれあいトレーニングハウス』を開設する事になりました。
詳細については、下記事項で確認下さい。
たくさんの皆様にご利用していただきますよう、宜しくお願い致します。
記
開催場所 ■ 緑・福祉会館 1階
開催日時 ■ 毎週 火曜日 午前10時~11時
*講師の石田忍先生
(健康運動指導士・介護予防運動トレーナー)
木曜日 午前10時~11時
*百歳体操DVD
※但し、祭日、お盆、お正月など、ふれあいの家が休日の日は中止です。
・入会金は要りません
会費 ■ 100円/回 但し、初回は無料です。
◆ 2013年度(平成25年度)
鶴見区緑地域のゴミの分別収集方法
平成25年10月1日よりゴミの分別収集方法と収集日が一部変更となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ごみのマナーABCにも詳しく解説されています。
なお、各町会で廃品回収等を行っている場合はそちらを優先させてください。
(お問い合わせは各町会へ)
長野県出張報告
実施日: 平成25年2月9日~11日
出張先: 9日 長野県長野市
10日 〃 須坂市
11日 〃 小布施町
目 的: 長野県を広く紹介しているエイジェントである『ビープラスワン社』の
服部社長の紹介で、今般NPO緑・ふれあいの家とNPO榎本地域活動協
議会の木村会長を含めて都市間の人的交流・野菜や果物などの販売活
路の開拓を目的とした。
概 要: 9日 長野市は須坂市を訪問目的であった為、素泊まりとなった。
10日 10日9時半に須坂市の朝市を見学した。
朝市では、さすがに野菜展示は少なかったが、お味噌・蕎麦・お米・
お酒や手作りの人形などが種類も沢山あり、市の観光センターで売ら
れていた。
街全体が自然の中で育まれ、点在する歴史館や須坂の雛人形など、
見どころも豊富にあった。
夜には須坂市の三木市長にもお出ましを願い、今後の双方の交流につ
いて意見交換を行った。
最後に、共に発展を願い三木市長より鶴見区の都倉区長宛に親書を
預かり後日手渡した。
11日 小布施町には11日10時にお邪魔した。
高野リーダーに小布施町の概要をレクチャーして貰い、その後小西
副町長をご紹介戴いた。
小布施町は大変纏まりがあり、しかも人的財産を上手に使いながら
地域の活性を行っていた。
私達が見習うべき所が随所にあって、考え方も現代社会と同期してい
る事に歓心した。
観光だけではなく、付加価値のあるプレゼンにも魅力があった。
総 括: 大変短くしかも駆け足での視察であったが、素朴な人達が一生懸命頑
張っている そうした姿に感じ入り、物販だけではなく双方の人的交
流が大切と思われた。今後、組織体制を整え、納得のできるお付き合
いを展開する必要がある。
平成25年2月12日 久木勝三
まちなか世界一ミュージアム誕生
緑地域の小学6年生と中学1年生が手がけた「まちおこしプロジェクト」
工夫を凝らし、手作りレジャー施設を造りました!

実際の長さはどのくらい?
世界一身長の高い人は?
世界一身長の低い人は?
マイケルジョーダンの垂直跳びは?
世界一細い家の幅は?
世界一小さな馬は?
世界一長い脚は?
etc
そんな長さを直感的に感じて楽しめるのが、『まちなか世界一ミュージアム』です。
【開催場所】
緑・ふれあいの家(正面壁・公園内)
緑社会福祉会館(正面壁・門扉)
Josin 店内1F北側
2丁目3番地角掲示板(上部・下部)
◆ 2012年度(平成24年度)
第2回 緑いどばたクラブ開催のご案内
開催日 4月20日(土)午後7時~
開催場所 みどりふれあいの家
会費 1,500円
規則や議題はありません・・・・。
皆さんの思い出作りが、目的かな?
適当に集まり、そして好きなことを話し合ってみませんか ?
もちろん、誰でも参加できますお待ちしています。

「みどりふれあい市」の野菜は、緑地域と縁があってつながった生産者の方々がつくられたものです。この市を通して、私たちの命をつなぐ食は、都市と農村がつながって成り立っていることが実感できます。どうやってつくられたのかわかるものを食べることができるという安心感があります。そして違った土地に暮らす人との交流が、わくわくした思いや新しい驚き発見をもたらしてくれます。 このような思いやつながりを、より充実したものとするために、この市での野菜の売り上げを私たち緑地域の暮らしの安全・安心を守る活動に生かしていくために次のような仕組みとすることを提案します。
 NPO法人 緑・ふれあいの家
NPO法人 緑・ふれあいの家